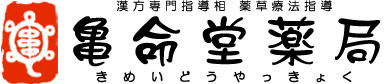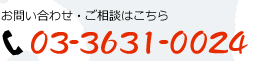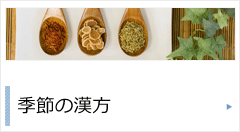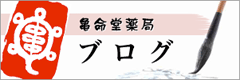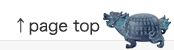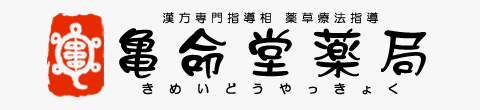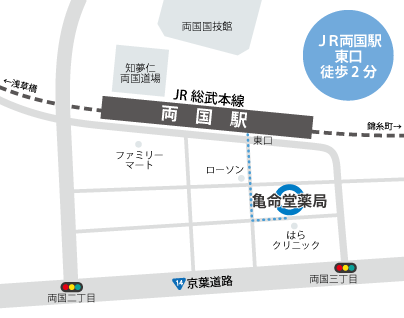亀命堂薬局 | 創業大正14年 1925年 濹東随一の漢方の老舗です。
生薬のご紹介
| 漢方処方・製品の主な原材料となる生薬の中でも代表的なものをご紹介いたします。 |
| 田七(でんしち)鬱金(うこん)枳殻(きこく)鶏血藤(けいけっとう)霊芝(れいし) |
| 白朮(びゃくじゅつ)竜骨(りゅうこつ)大黄(だいおう)土別甲(どべっこう) |
| ベトナム桂皮(べどなむけいひ)薬用石膏(やくようせっこう) |
| 朝鮮人参[白参・紅参](ちょうせんにんじん[しろ・あか])冬虫夏草(とうちゅうかそう) |
| 刺五加(しごか)木天蓼(またたび) |
 |
田七
(でんしち) 田三七、三七、金不換などの別名があります。田七人参というのは日本の近年の呼称です。 中国の明の時代に本草綱目に記載され、昭和50年代ころから日本にも知られてきた中国雲南省の生薬です。 |
||
戦争の時にひどい打撲や金瘡(刀、槍など武器による負傷)に使用されたもので、ベトナム戦争で雲南白葯という中成薬が出血多量の兵士の治療に使用され、注目されました。 肝臓疾患、心臓疾患などに有用であることが分かったのはその後の基礎と臨床の医学の成果です。 瘀血(古くなり滞り、また病的に発生する機能を喪失した血液。がんなどの腫瘍も瘀血と考えることが多い。)全般に使用します。贋偽品があり、品質にも注意が必要な生薬です。 |
|||
 |
鬱金
(うこん) 近年、有名になった生薬です。宇金 川玉金などの別名があります。一般的な漢方処方に使用されることはありません。亀命堂薬局の先代も先々代も生薬としてウコンを扱ったことはないということでした。 |
||
植物名(ハルウコン、ウコン)と生薬名(鬱金、薑黄と近縁の我朮)に産地を含めた混乱があり、生薬学を学ぶ者には面倒な生薬です。ウコンをアキウコンという和名で表示することがありますが、正式の和名ではないようです。 ウコンは香辛料、染料のターメリックです。カレー、沢庵漬の着色に使用。 利胆、健胃作用はあるものの肝臓病の治療には向きません。 |
|||
 |
枳殻
(きこく) ミカン科のダイダイまたはナツミカンなどの未熟果実を乾燥したものです。丸のままを枳実、2横割にしたものを枳殻といいます。 消化器系の機能促進、排膿散などの効能があり、胸腹部のつかえ、腹痛、膨満感、便秘などに用いられます。 |
 |
鶏血藤
(けいけっとう) この生薬も近年になって日本に知られるようになりました。 中国雲南省、広東省などに産するマメ科の植物の茎を乾燥したものですが起原植物は1種(「種」は分類の単位 「属」の下位)ではなく、複数あります。 補血、行血の効果があり、貧血性の生理不順、筋骨の麻痺、膝腰の痛みなどに使用します。 |
 |
霊芝
(れいし) サルノコシカケ科のキノコですので植物ではなく菌類です。日本ではマンネンタケを霊芝としています。 「神農本草経」という後漢から三国時代に成立した古い薬物書に収載されています。神農本草経には霊芝の色による薬効の区別がありますが無視してよい区別です。 |
||
産地による薬効の差があるようで、主に免疫系(アレルギー 腫瘍など)に効果のあるものと循環器系(血圧など)に効果のあるものとを区別することがあります。 |
|||
 |
白朮
(びゃくじゅつ) この生薬は類似生薬の蒼朮(そうじゅつ)とともに漢方処方にかかせない重要なものです。上記、霊芝と同様、神農本草経に収載されていますが、起原植物も複数あり、昔のものがどのような区別をされていたか不明です。 |
||
亀命堂では古立蒼朮という冬季に白色の結晶を綿のように析出するものを賞用します。白朮はどちらかというと虚弱者、心臓の機能の低い場合などに用い、蒼朮は効果の切れ味がよく、消化器の水毒(非生理的な過剰で冷えなどをともなう病的水分)の排除、筋肉や関節の疼痛に使用する処方に配合します。どちらも香の良い生薬です。 |
|||
 |
竜骨
(りゅうこつ) 学術表現では「新生代の化石哺乳動物の遺骸が永津地層中に埋没し、骨格、牙、歯、角などが粗鬚質に変化した化石」(原色和漢薬図鑑)です。象、犀、鹿、牛などの化石で花竜骨(写真のもの)が真正品ですが日本薬局方では「大型ほ乳動物の化石化した骨」と簡単です。 |
||
精神安定作用があり、牡蠣(カキの殻)とともに桂枝竜骨牡蠣湯などに配合。また、収渋という身体から精気がもれ出るようなときに使用します。重要な生薬です。 |
|||
 |
大黄
(だいおう) タデ科のダイオウ類の根茎を乾燥したもの。 瀉下、清熱、活血、駆瘀血の作用があり、便秘、熱性疾患、打撲、月経異常などに用いられています。 |
 |
土別甲
(どべっこう) スッポン(またはシナスッポン)の背中側の甲羅を乾燥したものです。 補陰、止痙などの効能があり、発熱、寝汗、痙攣、ひきつけなどに用いられます。 |
 |
ベトナム桂皮
(べとなむけいひ) クスノキ科のケイ(トンキンニッケイ)の樹皮を乾燥したもの。 補陽、発汗、解肌、止痛などの効能があり、手足の冷え、腹痛、下痢、のぼせなどに用いられます。 |
 |
薬用石膏
(やくようせっこう) 天然の含水硫酸カルシウムを主とする鉱物です。 清熱、止渇、沈静の効能があり、熱性疾患にみられる高熱や口渇、炎症のあるむくみや痒みなどに用いられます。 |
![朝鮮人参[白参・紅参]](/dcms_media/image/syoho_06_img12.jpg) |
朝鮮人参[白参・紅参]
(ちょうせんにんじん [しろ・あか]) ウコギ科のオタネニンジンの根を乾燥したもの。 高麗人参や朝鮮人参と呼ばれることもあります。 補気、健脾、強壮などの効能があり、疲労や体力の低下、食欲不振、消化不良などに用いられています。 |
 |
冬虫夏草
(とうちゅうかそう) 滋養強壮作用がある、慢性疲労や病後の回復によい、といわれています。 |
 |
刺五加
(しごか) 不眠症や自律神経失調症に効果があると考えられています。 集中力を高め、疲労回復にも使われます。 |
 |
木天蓼
(またたび) 猫が大好きなことで知られるあの「マタタビ」です。 冷え性、神経痛、リュウマチ、腰痛などに効果があります。 |
Copyright © Kimeido Yakkyoku. All Rights Reserved.